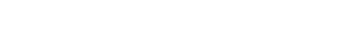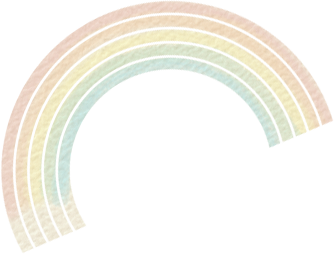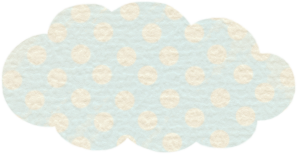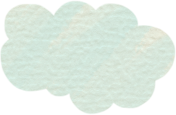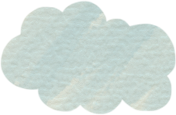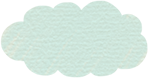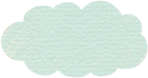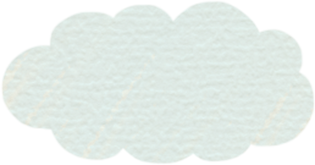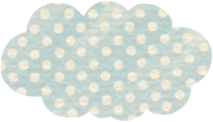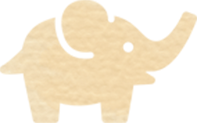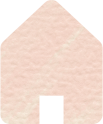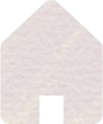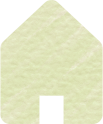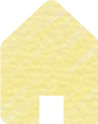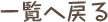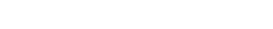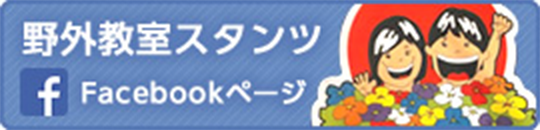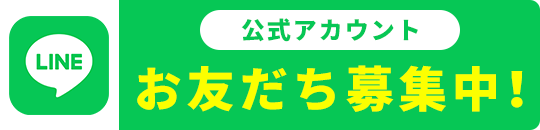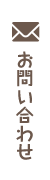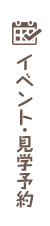ブログ&イベント詳細
スタンツおだしの授業 その1
ママが作ってくれるお料理って、どうして美味しいのかな。
お料理の中でも、色んなのがあるよね。カレーライスにハンバーグ、スパゲッティにピザ。
お魚のお刺身に、エビフライ。朝ごはんはお味噌汁。おうどんも大好きだね。
全部味が違うね。どうして色んな味ができるんだろう。
美味しい味にするには、どうしたらできるのかな。
食べる事が大好きな子ども達に、「美味しい味を知ってもらう」事を目的に、
今回「おだしの授業」を行いました。
美味しい味って、本当に沢山ありますね。
—–和食にしようか、洋食でいこうか。それとも中華にしようか。洋菓子にしようか、いやいや和菓子も良いなあ。
どんな味を知ってもらうかと、色々と考えてみた結果、和食の味を伝える事にしました。
子ども達が離乳時期に一番初めに食べるのはお粥や、くたくたに煮たおうどんや、薄味の和風だし。
「ねえ、おうどんのスープって、どうやったらできるのかなあ。お鍋にお水入れて、ぶくぶくしたらできあがりかなあ」
そう、子ども達に問いかけてみると、子ども達からは色々な意見が。
「人参切って、ジャガイモいれてー、できあがり」
「えー、それじゃあ人参の味しかしないよ」
「じゃあ、りんごかな」
「ママねえ、なんかふわふわしたのを入れてね、ハンカチかなあ、それにじゃーしてね、ぎゅっと絞るの」
「ほおおー」


もしかしたらそれって……きちんとお出汁をとっているのではと思えるような意見も出てきましたね。
「皆さん、皆のママは、お料理をする時にちちんぷいぷいのぷいっと、簡単には作っていないのです。みんなの事を想いながら、色んな手間をかけて作っているんですよー」
「へえええ」


「ではでは、美味しい美味しいスープになる為に必要な材料を幾つかもってきたのでお見せします。」
「まずはこちら。皆さん何に見えます?あっ、ちょっと静かにして耳をすませてね。」
と言いながら、手にしたカツオを叩いてみる。すると、「堅い!」「木みたい」との声が。
中には「ブリかな?」と、かなり近い答えの子も。
「木とか枝みたいに見えますけれど、これは実はお魚なんですね」
「お魚?!」
「そうです。これはカツオと言ってブリやマグロと同じ大きな魚です」
和田先生が、カツオの写真を大きな紙に印刷したのを見せてくれました。
海で元気に泳いでいる魚がどうしてこんなに硬くなってしまったのかを説明した後、
次は昆布を見せてあげました。

「昆布は天白公園とか大高緑地に生えている草では無いんですねー。
冷たいつめたーい、北海道の海に」
「北海道知ってる!」
「そう、その北海道や東北の海で育つ、海の草です。どれぐらい長いのか調べてみましょう」
と、言う事で袋に詰められていた羅臼昆布を広げてみると、なんと2メートルを越えました。
そして、昨日の晩からつけておいた昆布を箸でひきあげて、昆布の淵からしたたり落ちる透明の粘液を見せてあげました。この滑った液が美味しさの素ですね。


他にも、どんこ(干し椎茸)も見せてあげました。
煮干しも見せてあげたら良かったですね。
「さて、カツオと昆布、どんこを観察しましたね。昆布は小さく切ってお鍋に入れる。どんこもお鍋の中に。じゃあ、カツオはこの塊のまんまでお鍋にドボンなんでしょうか?」
子ども達は笑いながら、「ドボンしない」と。
「そうですよね。こんなに硬いまんまでは、溶けないですよね。じゃあ、細かく削りましょうか」


そこで和田先生が、鰹の削り器を見せてくれました。
工作でのこぎりを使用した事のある子ども達。削り器についている鋭い刃を見て、
それは注意して扱う道具だという事に、すぐに気がついていました。
そして鰹の頭と尾の部分を知らせ、どのあたりを削れば美味しいスープ(おだし)になるのかを伝えます。
子ども達が静かに見守る中、しゅっしゅっとカツオの削れる音が聞こえてきます。
そして次第に漂ってくる鰹節の香に、子ども達は敏感に反応します。
「皆さん、教室の中、とっても良い匂いがしますね。美味しい香ですね。では今から、皆でこの美味しいおだしを作ってみましょう」
そう声をかけると、子ども達は気合に満ちた表情で大きくうなずいていました。