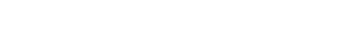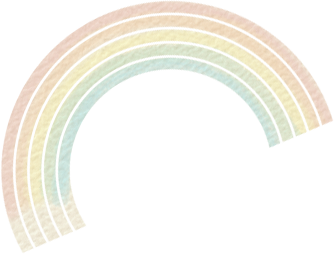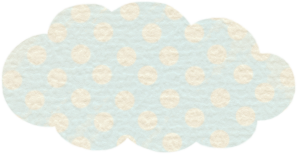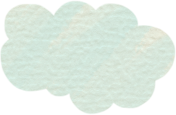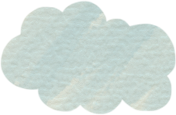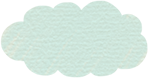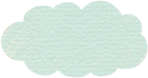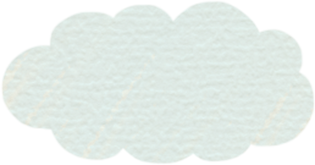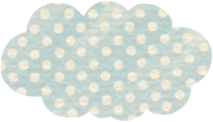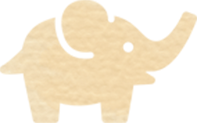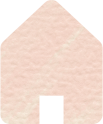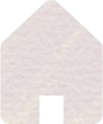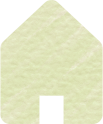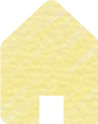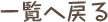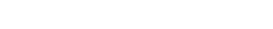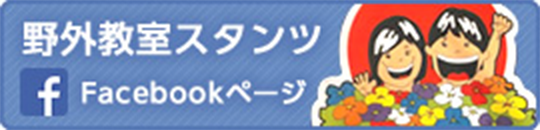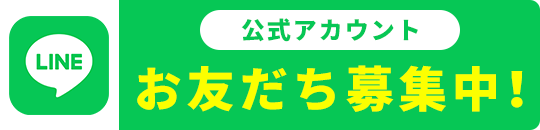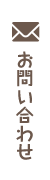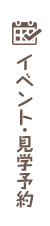ブログ&イベント詳細
Do曜塾GENKI塾Cコース 活動報告
今日はセンターの園庭を利用して、火おこしに挑戦しました。 来週の野外料理(パンケーキ作り)を行う前に、火おこしをじっくりと取り組んでみることにしました。火を起こすって、どうやったらできるんだろう。お家では、ママがスイッチを押したりひねったりするとガス台から火がボワッと起こります。オール電化の御家庭でしたら、火を見る機会はもっと少ないかもしれませんね。園庭にはスイッチをひねると火がでてくるような物はないし、魔法を使うこともできない。さあどうしようと考えてみると、子ども達からこんな意見が出てきました。 ①板に穴があって、そこに棒をつっこんでゴリゴリこする。(原始時代の日おこしの道具をイメージしているのだと思います) ②石を2つあわせて叩いてみる(火打石の事を言っているのかな?) ③「うちわを使って、ぱたぱたあおぐ!」(おっ、どこかでBBQを経験したのかな?) この3つの意見。良く考える事ができましたね。しかし、①と②の方法で火おこしをしようとすると、きっと一日かけても子ども達の力では火をおこすことが難しいと思います。③の「うちわを使って、ぱたぱたあおぐ」を絡めた行動が、一番火おこしに近い事を子ども達に伝えました。すると、子ども達からこんな意見が。 「木とかないの?」 「マッチは?」 「お父さん、木をね、こーんなふうに集めて下から火をつけてた」 おおー!なんとなく、火おこしのイメージができています。木とか、マッチとか火をつけるもの、火を長く燃やすものを考える事ができました。 そこでみんなに、「実は園庭の色んな所に、火をおこすための道具や材料があるから探してみよう」と声をかけました。すると子ども達は宝物探しをするかの様に、いきいきとした表情で園庭中を物色します。子ども達が集めてきたのは、焚き付け用の薪と割りばし・新聞紙・マッチ・枯葉。 じゃあ、どうやって火をつけたら良いのか、グループに別れて焚火の準備をしました。準備の前に軍手を着用。これまで金槌やのこぎりを使う時は片手だけ軍手をはめていましたが、今回は両手。軍手をはめるのは、なかなか大変です。五本の指が上手くはまらない状態の子を見て、優しく手伝ってあげる姿も。
手袋をはめた後は、全員にマッチを配りました。マッチをこするのは今後行いますが、まずは「マッチって、どんなものなんだろう」と、マッチをじっくりと触ってみることに。マッチの頭の部分、色がついている所は火をつける為の薬が塗られていること。薬の部分は舐めないこと。薬の部分を地面に擦り付けると火がつかないこと。そして、指でつまむと、マッチはけっこう短いこと。 「火が着いたら怖い」と言う子がいました。そうですね、つまんだ部分から近い所で火が着いているのを想像すると、ちょっと怖いですね。まずは、「怖い」と感じる事が大切。 怖いけれど、正しい使い方がわかると、怖くない便利な物。これは一日では実感できるものではないので、これから少しずつ感じると良いですね。 そして3つのグループごとに薪をくべたのですが、円錐状にくべたチーム、薪を横に並べたチーム、とにかくぐちゃぐちゃにくべたチームと、それぞれの形になりました。本当は、「焚火なら、こんな形が良いよ!」と見本を教えたいところですが、今日は「たとえ、火が着かなくても良い。一瞬に燃えてしまっても良い。火がどんなふうについて、どんなふうに消えていくのかを見せてあげたい」、そんな思いでやってみました。 そして着火してみたところ……。
「あっ、(火が)着いた!」と喜ぶ子ども達。しかしすぐに、「あれ?もう消えちゃう」と言う子達も。薪のくべかた次第で火はすぐに消えてしまいます。そこで登場したのが、うちわ。下からゆっくりと、火の中に空気を入れるように扇ぐと、静かになっていた火が一気に勢いを取り戻します。
かわるがわる団扇で仰ぎました。火が燃え尽きた頃には、活動終了の時間が近づいていました。「先生、パンケーキ作らんの?」と聞く子が数人。 来週は、いよいよ火起こした火を使って、お料理をします。 Cコースの皆さん、風邪には気をつけて。次週、皆で野外料理を楽しみましょうね!!