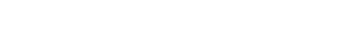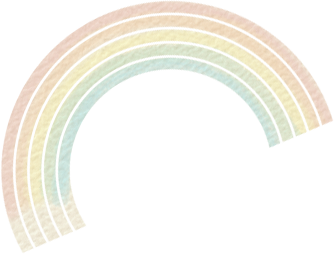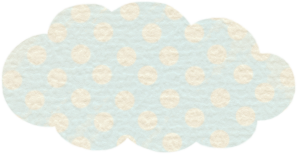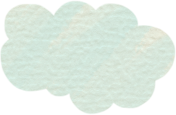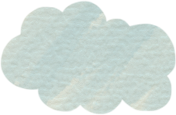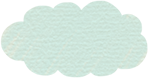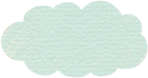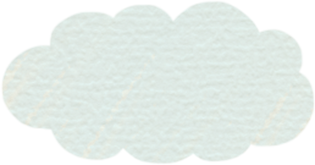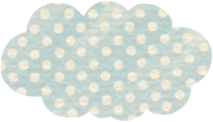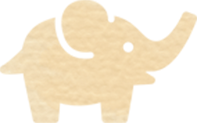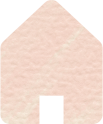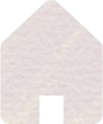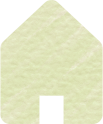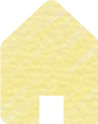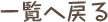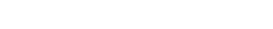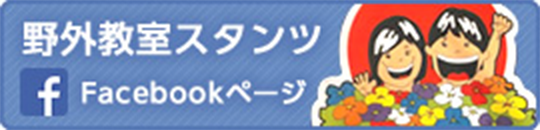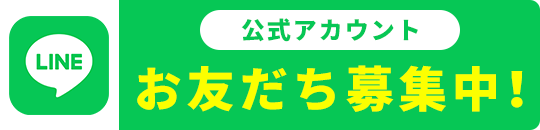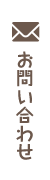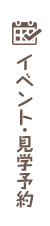ブログ&イベント詳細
MEIKYO塾長コラムあんぱんち11月「勉強の意味」ー名教
塾長コラム「あんぱんち」11月号です。(塾生新聞『ほっぷすてっぷじゃんぷ』に掲載中!)
今月は,「勉強の意味」について考えています。
お子様たちの通う小学校では、学芸会、作品展が行われ、中学校では合唱コンクールなどが行われました。どれも2学期の一大イベントですが、各自の役割を果たし、それぞれが達成感を味わってくれていたらいいなと思います。現実に戻って、中学、高校生は期末テスト、小学生も学期末のテストが行われる時期ですね。残り少ない2学期ですが、学習面の締めくくりもしっかりと成し遂げてほしいですね。
さて、先日、あるところにいると、近くで地域のおじいさん、おばあさんがお茶を飲みながら、雑談をしていました。健康の話、温泉旅行の話、お金の話・・・。日常の何気ない会話に、ほのぼの感じ、耳を傾けてしまいました(知り合いがいたから、盗み聞きしたわけではありませんよ)。
そんな会話の中、「年末ジャンボ宝くじがもうすぐ発売されるなぁ。」という話がありました。「オレ、買いに行く。夢だがや。」とか、「あんなもの当たるわけがないから、ワシは買わん。」とか、「私は、名駅まで毎年買いに行くわ。」「そんなもん、アピタで買っても同じだわ。」と会話は続いていきました。すると、その中にいらっしゃった顔見知りのおじいさんから、突然話が振られました。「そういえば、この人、先生だわ。宝くじが当たる確率は、名駅のチャンスセンター(名古屋でよく当たりが出ると言われる有名な場所ですよね)と、近所のスーパーの売り場のどっちが高いんじゃ?」
大変失礼ながら、純粋な子どものような質問に、驚きました。でも、確かに、素朴な疑問ですね。そういえば、我が家でも、妻と子がそんな会話をしていたような気もします。
算数、数学では、小学校5年生の割合、中学2年生の確率の単元で、学習します。数学が身近に感じられる題材です。
さて、答えです。当選確率は、どこで買っても同じです。よく当たると言われる売り場に、「○億円、○本!」なんてたくさん書いてあるのは、確率の問題ではなく、販売枚数が多いからたくさんの当たりが出ているだけのことです。裏を返せば、よく当たる売り場は、外れている本数も多いのです。確かに、販売枚数の少ない売り場には、売り場にくじが届いた段階で、すでに当たりが入っていない可能性が高く、逆に販売枚数の多い売り場には、その可能性は低くなるとは言えますが、全体の販売枚数における当たりくじの割合は、どこも同じです。
例えば、当選確率1%の宝くじがあったとします。販売枚数100枚の売り場からは、100×0.01=1で,1本の当たりが出ます。一方、販売枚数1000枚の売り場なら、1000×0.01=10で、10本の当たりが出ます。この10本という数字を大々的に、「当売り場から10本も当たり出た!」と広告するわけです。それを見て、よく当たる売り場だからと言って、交通費をかけ(それで、もう1枚余分に買った方が、当選確率は上がるかもしれませんね)、長い行列に並んでいるのは、数学的に言えば、あまり意味のないことと言えるでしょう。「いや、その夢を買いにいく時間も楽しみなんだ。」という声が聞こえてきそうです。そこは、数学では否定できませんが。
子どもたち、とりわけ中学生が「先生、こんな数学なんの役に立つの?」とよく言います。生活の中にはたくさんの数字があふれています。こんな話題にも触れながら、子どもたちに学ぶ意味について伝えていこうと思っています。
勉強とは、世の中や社会に、自分がどうつながっていくかを学んでいるんだよと思っています。
塾長 西川 陽祐