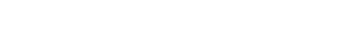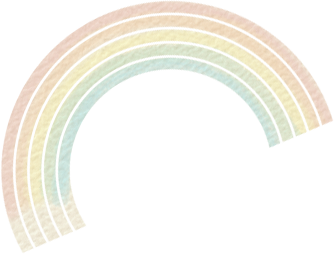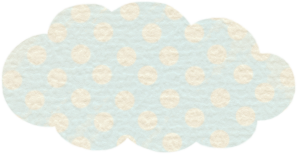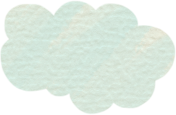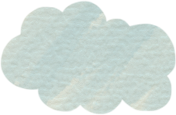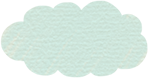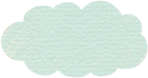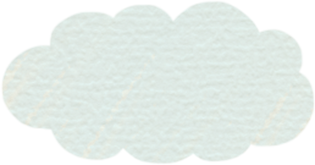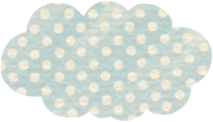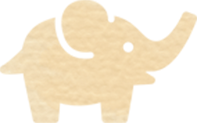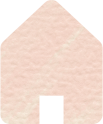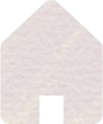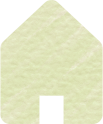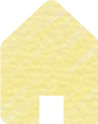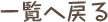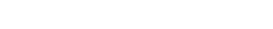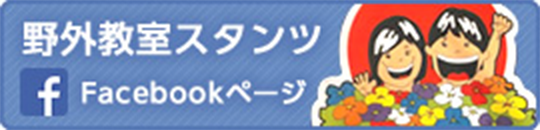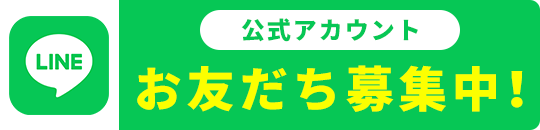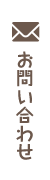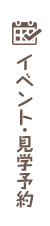ブログ&イベント詳細
スタンツ冬越しの虫をさがしに
1月20日から22日の3日間。年少クラスの子供達はずっと虫を探していました。
えっ?こんなに寒い時期に虫はいるんですかって?
いるんですよ。
幼虫のまま、成虫のまま。形も様式も様々ですが
虫たちはこの厳しい寒さから上手に身を守る術を知っています。
もちろん、餌となるものもこの時期はなかなか手に入りません。
なので、餌をとらずとも生き続ける為に、虫たちは極々ひっそりと生活します。
完全に朽ち果てる前の、わずかに水分が残っている木の幹の中、
たくましい顎を使って穴を掘り、その中にぴったりと体を寄せて
春が来るのを待ちわびる虫。
剥がれかけた木の皮の中にびっしりと群れをなして
まるで肌を寄せ合うかのようにじっとしている虫。
黒光りする硬い殻をまとった成虫の姿からは想像できないような
やわらかな身体でもぞもぞと動く虫。
草木も枯れて静まり返った森の中で、そんな虫たちの姿を見つけることができた時、
子どもたちの表情はいきいきと輝きます。
ひらひらと花のまわりを飛ぶこともなく
驚くほどの飛距離を見せ付けることもなく
耳元でつんざくような音を聞かせることもありません。
けれど、冬の虫探しはとても楽しいのです。
そんな楽しさを十分味わうには、やはり自分で見つけるしかありません。
はじめは「先生見つけてー」「先生、どこを捜したらいいのー」と先生の後を
追いかけていた子達も、経験を積んでいく中で
虫たちがどんなところで冬越しをするのかわかってきたようです。
手で捜せるところは素手で掘り、難しいところはスコップや金づちを使います。
スコップや金づちは下手に扱うと怪我をしてしまいます。また、故意でなくても
相手を傷つけてしまいます。
仲間との協調性、道具を扱う時の注意力。
そしてむやみに自然の環境を変えないこと。
時には先生から指導を受けながら、子供達は探し続けます。
ここが駄目なら、場所を変えてみよう。
この木には、もういないかもしれない。
虫だって、誰にも邪魔されずに静かに冬を過ごしたいはず。
そう簡単には見つけさせてくれません。
それに、はじめは「カブトやクワガタの幼虫を見つける」と息巻いていた子達も
そういった花形のものが、どこにでもごろごろしているわけでは無い事に気づきます。
最初は随分地味な虫に対して「ちぇっ」と舌打ちしていた子達も
探し続けるうちに、虫の名前を覚えて、少しずつ親しみを感じる様に。
虫探しの様子(動画)はこちらから
虫探しの合間に、木の切り株を見つけて友達とひとやすみ。
森の中での寛ぎ方。自分で見つけた場所だから、心からホッとするね。
外はとても冷たい風が吹いていました。
けれど森の中は、春の光がいっぱいに満ち溢れていましたよ。